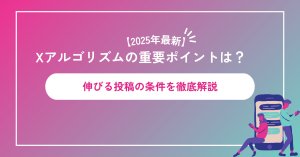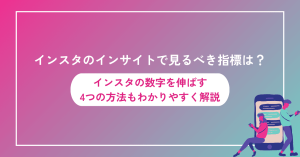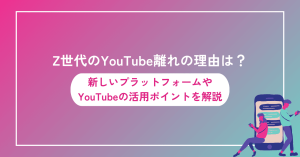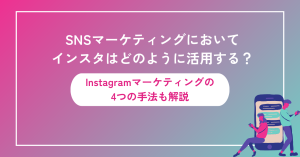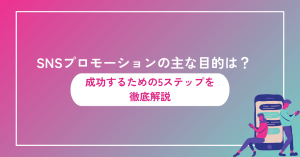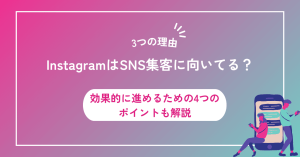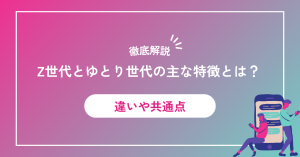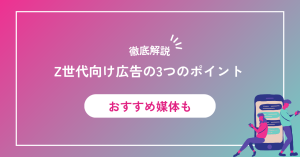Z世代の流行ジャンルからわかるZ世代の主な価値観や流行傾向
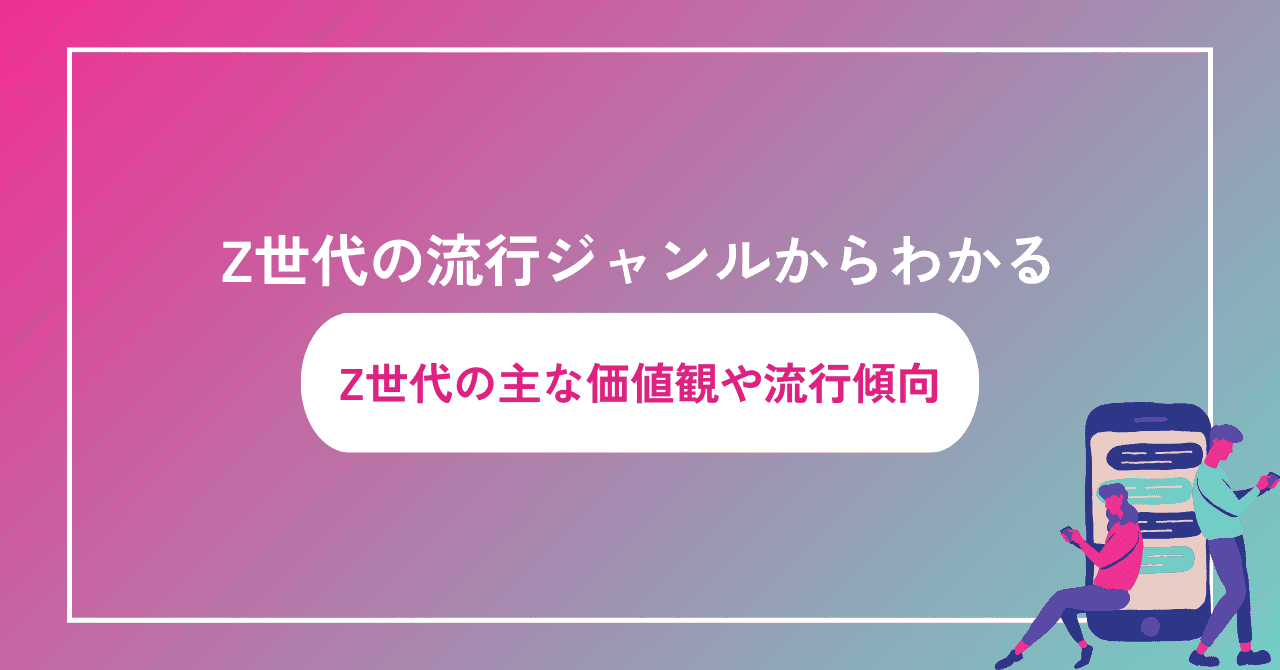
近年、Z世代の流行はこれまでの常識とはまったく異なる形で生まれています。
テレビや雑誌といった大規模メディアからではなく、SNSやコミュニティを中心に、身近な人やナノインフルエンサーの発信から自然に広がるのが特徴です。
しかし、こうした流行は従来型のマーケティングでは捉えきれません。
本質を理解しないままアプローチすれば、Z世代からは「仕掛けられた流行」と見抜かれ、かえって距離を置かれるリスクさえあります。
そこで本記事では、Z世代の流行を形づくる 7つの注目ジャンル と、背景にある価値観や行動傾向を整理します。
ファッションや食、SNSの使い方から、コミュニティ発信型のトレンドまでを具体的に解説し、マーケティングに活かせるヒントを探っていきましょう。
Z世代の流行や価値観を理解したい方は、ぜひ参考にしてください。
Z世代の流行を読み解く7つの注目ジャンル
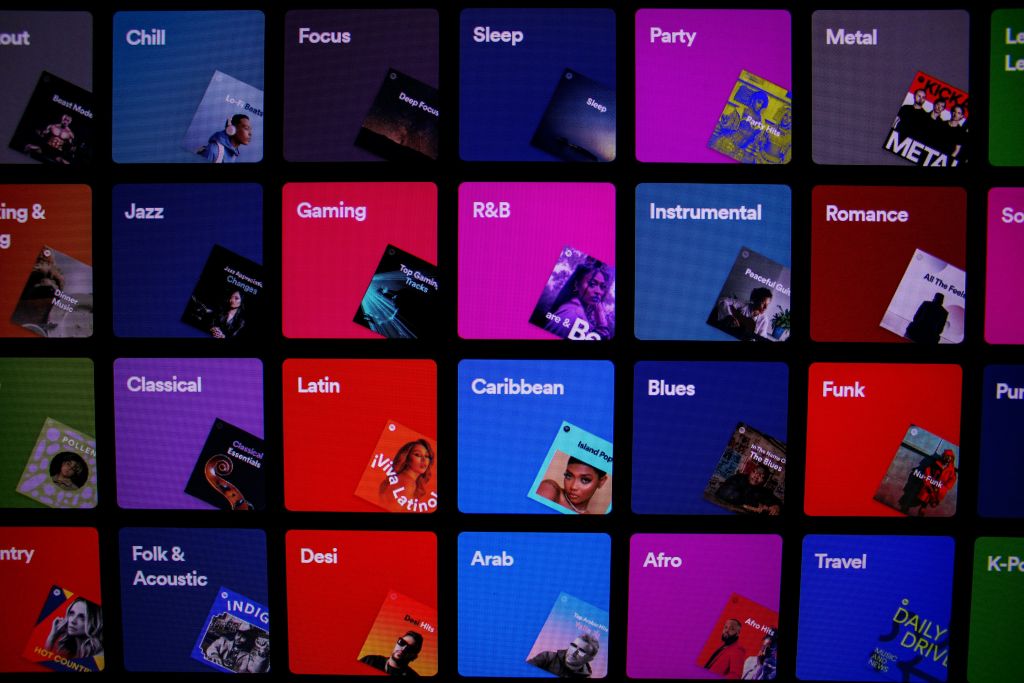
Z世代の間で生まれる流行は、日常のあらゆるシーンに広がっています。
ファッションや食べ物からSNS、言葉遊びに至るまで、彼らの価値観や生活スタイルがそのまま反映されるのが特徴です。
ここでは、2025年の7つのジャンルを整理し、どのような流行が注目されているのかを見ていきましょう。
ファッション
2025年のZ世代ファッションは、個性と遊び心を大切にしながら、ガーリーさや幻想性、そして自由な組み合わせを楽しむスタイルが目立っています。
これまで主流だったY2Kブームが落ち着きを見せ、新たな価値観を反映したトレンドが広がっています。
トレンドのキーワードとスタイルをまとめると、以下のとおりです。
| パステルカラー | パステルピンクをはじめ、ライトブルーやライラックなどやさしい色合いが全体的なトレンドに |
| ウィッシュコア・バレエコア・ネオ森ガール | ガーリーで幻想的な雰囲気やナチュラル志向を取り入れたスタイルが台頭 |
| 平成リバイバル+グランジ | 平成時代のファッション要素が再評価され、グランジテイストと融合 |
| 華やかな装飾主義 | 存在感のあるシルエットや装飾性の高いアイテムがカムバック |
SNSを通じてトレンドが瞬時に拡散され、国境や固定的なファッションリーダーを越えて多様なスタイルが広がっています。
従来の「何が正解か」ではなく、自分の感覚や世界観に合ったファッションを取り入れる流れが、Z世代のファッションを形づくっています。
食べ物・カフェ
2025年のZ世代が注目する食べ物やカフェは、SNS映え・健康志向・体験性をキーワードに進化しています。
見た目の可愛さや話題性はもちろん、推し活や交流の場としての機能も重視されており、食は単なる「味わうもの」から「楽しむ体験」へと広がっています。
Z世代に人気の食べ物・スイーツは、以下のとおりです。
- アサイーボウル
- フローズンヨーグルト
- トゥンカロン
- 10円パン
- ドバイチョコレート
他にもZ世代に人気のカフェには、以下のようなものがあります。
- 無機質カフェ
- 体験型カフェ
- 夜カフェ
- 推し活カフェ
Z世代にとって、食べ物やカフェを選ぶ際の基準は「映え」だけではありません。
SNSで情報を収集し、写真映えするかどうかを意識する一方で、実際に味やクオリティの高さも重視する傾向が強まっています。
健康志向の高まりから、ビーガンやオーガニック、グルテンフリーといった多様な食文化に対応する店舗も支持を得ています。
美容・コスメ
Z世代にとって美容・コスメは「価格以上の満足感」と「ブランドの世界観」の両立が必要です。
コスパに優れたプチプラを日常に取り入れつつ、憧れのデパコスで特別感を楽しむスタイルが広がっています。
| rom&nd(ロムアンド) | 高発色・色持ちが良いリップで支持。プチプラながらデザイン性も高評価 |
| CANMAKE(キャンメイク) | 種類が豊富で「手軽にトレンドを試せる」点が魅力 |
| CEZANNE(セザンヌ) | ドラッグストアで手軽に購入可能で、カラー展開も幅広い |
| Dior(ディオール) | かわいいパッケージとブランド力で憧れの存在 |
| Curel(キュレル) | 敏感肌向けで、マスク緩和後に注目度上昇 |
| ByUR(バイユア) | 美容液感覚のベースメイクが特徴 |
Z世代は、「プチプラで盛れる日常」+「デパコスで特別感」+「肌に優しいケア」を使い分け、シーンや目的に合わせた美容スタイルを築いています。
アプリ・SNS
Z世代にとって、SNSやアプリは日常の情報収集・自己表現・コミュニケーションの中心的な存在です。
利用するサービスごとに目的を使い分けるのが特徴で、従来の人気アプリに加えて「盛らないリアル」を重視する新しいSNSも広がりを見せています。
主要なSNSの利用傾向は、以下のとおりです。
| ・ファッションやグルメ、インテリアなどの情報収集やショッピング機能の活用が中心 ・ハッシュタグ検索で欲しい情報を探す行動が定着 | |
| YouTube | ・動画コンテンツ視聴の場として依然利用率が高い ・エンタメから学習まで幅広い用途で支持 |
| LINE | ・もっとも基本的な連絡ツール ・友人とのグループチャットや日常的なやり取りに必須 |
| TikTok | ・息抜きや娯楽の中心SNS ・おすすめ動画や参加型コンテンツを通じて流行の発信源 |
| BeReal. | ・加工や演出を排したリアルな日常をシェアできる「映えないSNS」 ・通知後2分以内の撮影 ・投稿ルールが独自で、飾らない人間関係を好むZ世代の価値観と一致 |
Z世代は「映えるSNS」と「リアルを重視するSNS」をシーンごとに使い分けるのが特徴です。
流行は単なる一過性のブームではなく、仲間と共有するための会話の通貨として機能し、FOMO(取り残される不安)や「自分らしい発信」への欲求と強く結びついています。
言葉・ネタ
Z世代における流行語やネタは、SNSと密接に結びつき、単なる会話の装飾ではなく「共感の通貨」として機能しています。
特にTikTokやSimejiのようなプラットフォームを通じて、リズム感やユーモア、シンプルな感情表現を持つ言葉が日常会話にまで広がるのが特徴です。
2025年上半期に流行した代表的な言葉・ネタをまとめると、以下のとおりです。
| エッホエッホ | ・フクロウの赤ちゃんの写真に添えられたキャプションが発端 ・TikTokで走る動きを真似た投稿がバズって拡散 |
| 今日ビジュいいじゃん | ・アイドルグループ「M!LK」の楽曲フレーズが由来 ・音源に合わせた動画投稿で浸透 |
| 〇〇界隈 | ・「推し活界隈」「風呂キャンセル界隈」など、趣味や価値観ごとのコミュニティを指す表現 |
| メロい | ・「エモい」をさらに推し活向けに特化した言葉 ・「推しにメロメロ」という意味で日常的に使用 |
| ほんmoney. | ・インフルエンサーkemioの発言から拡散 |
Z世代の流行語やネタには、以下のような共通点があります。
- ユーモアと脱力感
- SNS映え
- 共感とリアルさ
Z世代の流行語やネタは「意味」そのものよりも雰囲気・使いやすさ・仲間と共有できる感覚が重視されています。
ガジェット・アイテム
Z世代のガジェット・アイテム選びは、単なる最新技術の追求ではなく、デザイン性・SNS映え・ノスタルジー・コスパといった価値観を重視しているのが特徴です。
最新機能だけではなく「持っていて映えるか」「自己表現につながるか」が購入理由の大きな軸となっています。
流行中の注目ガジェットには、以下のようなものがあります。
| Nothing Phone (2a) | ・透明感のあるデザインで、SNSに投稿した際の映えを意識したスマホ ・コスパの高さも支持 |
| ポータブルプロジェクター | ・TikTok Shopで人気 ・Magcubicなどの小型モデルは手軽に大画面を楽しめ、友人とのシェア体験にも活用 |
| レトロiPhone・古いデジカメ | ・2000年代の「ホームボタン付きiPhone」やフィルムカメラ ・荒い画質のデジカメは、Z世代にとって「懐かしくて新しい」エモさを生むアイテム |
| Polaroidやビニールレコード | ・アナログの魅力と現代技術を組み合わせたハイブリッドガジェットも注目 |
流行の背景にある価値観は、以下のとおりです。
- SNS映えするデザイン性
- 遊び心と実用性のバランス
- ノスタルジーと自己表現
Z世代のガジェット消費は「最新=正義」ではなく、自分らしさやSNSでの共有価値を満たすものが支持されているのが特徴です。
エンタメ・推し活
Z世代にとってエンタメと推し活は、単なる趣味を超えて「生きがい」や自己表現の一部となっています。
特に「推し」を中心にした小さなコミュニティの形成や、ショート動画をきっかけとした音源バズ、ファン自身が参加できるコンテンツが人気の特徴です。
流行中のアーティスト・コンテンツの一例を挙げると以下のとおりです。
| AiScReam『愛♡スクリ〜ム!』 | ・TikTokで火がついた音源バズの代表例 ・学校やイベントでも広がり、ランキング1位を獲得 |
| M!LK『イイじゃん』 | ・リズム感の良いフレーズが「今日ビジュいいじゃん」などの流行語と共に拡散 |
| Mrs. GREEN APPLE『クスシキ』 | ・ダンス映えする振付が人気となり、ショート動画で拡散 |
背景にある価値観には、以下のようなものがあります。
- つながるけど染まらない
- 共感と自己表現
- 推し消費の拡大
Z世代にとってエンタメや推し活は、仲間と共感しながら自分を表現する文化であり、生活の中心的な存在となっています。
Z世代の主な価値観

Z世代を理解するうえで欠かせないのが、彼らの根底にある価値観です。
従来の世代と比べて、SNSの普及や多様性の尊重といった環境要因の中で育ったZ世代は、他者との共感と「自分らしい自己表現」の両立を大切にしています。
流行や消費行動の背景にもこの価値観が強く影響しており、彼らの動向を読み解く際には避けて通れない視点となります。
ここではZ世代の主な価値観を一つずつ見ていきましょう。
共感と自己表現のバランス
Z世代を理解するうえで欠かせないのは、「共感」と「自己表現」を同時に重視する姿勢です。
彼らは仲間とのつながりを求めつつも、自分らしさを失わないことに強いこだわりを持っています。
その背景には、SNSを通じて常に多様な価値観に触れてきたことがあり、流行を「会話の通貨」として共有しながらも、自分の感性でアレンジして発信する文化が根付いています。
具体的な行動を挙げると以下のとおりです。
- BeReal. で「盛らない日常」を投稿し、リアルな共感を得る
- TikTokやInstagram で流行のフォーマットを使いつつ、自分らしい編集や表現を加える
- 「〇〇界隈」 といった小規模コミュニティで、共通の趣味や価値観を持つ仲間とつながる
Z世代にとって流行は、単なるブームではなく、共感と自己表現を両立させるための重要な手段となっています。
取り残されないための参加型消費
Z世代の消費行動を語るうえで欠かせないのが「取り残されないための参加型消費」です。
FOMO(取り残される不安)を背景に、流行への参加自体が目的化し、仲間意識や自己表現と結びついている点に特徴があります。
彼らの価値観の中心には「つながるけど染まらない。」などの姿勢があります。
他者との共感を求めながらも、自分らしさを失わないことを大切にしており、この両立が流行参加の強い動機になっています。
具体的には、以下のような行動様式が見られます。
- SNS上で「乗り遅れたくない」などの不安が参加する動機に
- トレンドは「話題に参加できるための共通言語」として消費
- 重要なのは「それをやっている自分がどう見えるか」であり、SNS投稿によって自己表現を成立
- 「ゴシム4カット」や「BeReal.」など、誰でも気軽に参加できる形式が人気
Z世代にとって流行は「所有するモノ」ではなく「共感を得るために参加する体験」です。
企業がこの価値観に応えるには、単なる広告ではなく、ユーザー自身が流行の担い手となれる仕組みを用意し、共感から紹介へつながる設計を組み込むことが求められます。
SNSでの見せ方と共有欲求
Z世代がSNSを活用する理由の一つは、「共感」と「自己表現」の両立にあります。
流行の共有は「取り残されないため」の行動であり、同時に「流行を知っている=話題に参加できる」安心感につながっています。
Z世代の価値観の特徴を挙げると、以下のとおりです。
- 流行を「会話の通貨」として扱い、乗り遅れないために積極的に共有
- 徹底的に加工する「編集文化」と、BeReal.に代表される「ありのままを見せる文化」が共存
- ゴシム4カットや音源バズなど、誰でも気軽に真似できる形式が支持
Z世代のSNS行動は「共感を得るための共有」と「自己表現を際立たせる演出」が同時に作用しており、そこにこそ彼ら特有のSNS文化の本質があります。
Z世代の流行傾向

Z世代の流行は、従来の「メディア主導」や「有名インフルエンサー発信」とは異なり、小さな発信や共感の連鎖から広がるのが特徴です。
彼らにとって流行とは「単なるブーム」ではなく、自己表現や仲間との共感を生み出す会話の通貨として機能しています。
特に次の3つの傾向が顕著です。
- ナノインフルエンサーの影響力
- UGCから生まれる共感
- コミュニティ発信型のトレンド
Z世代の流行傾向を理解するためにもそれぞれの項目を見ていきましょう。
ナノインフルエンサーの影響力
Z世代にとって流行の起点となるのは、企業の大規模キャンペーンではなく、身近で信頼できる人からの発信です。
フォロワー数1,000〜5,000人程度のナノインフルエンサーは、リアルで共感性の高い情報源として、流行の「火種」として機能しています。
具体的には以下のような特徴があります。
- 広告色の強い発信よりも、距離感の近いナノインフルエンサーの体験談が支持
- 個人的な日常や失敗談など、Z世代が「自分ごと化」できる発信
- スメレビューアプリ「LIPS」などで見られるように、口コミ発信が大手広告以上の購買効果を生むケース
ナノインフルエンサーは、共感の連鎖を生み出す存在として、Z世代の購買行動やトレンド形成を左右しています。
企業にとっても、流行を一方的に仕掛けるのではなく、彼らと共に作り上げる戦略が不可欠です。
UGCから生まれる共感
Z世代にとって流行が広がる起点は、企業の仕掛けではなく、ユーザー自身の体験や発信=UGC(ユーザー生成コンテンツ)です。
UGCはリアルな共感を生み出し、拡散を促す「共感の連鎖」をつくる仕組みとして機能しています。
具体的にUGCが共感を生む理由は以下のとおりです。
- 一般ユーザーやナノインフルエンサーの投稿は「リアルな体験」として受け入れられやすい
- TikTokの音源バズや「ゴシム4カット」のような参加型コンテンツは、真似や編集を通じて次々と共感が広がりやすい
- 自分の感性で加工して「同じ流行に違う自分で参加する」編集文化が浸透
Z世代の「信頼できる情報源」として機能しながら、共感→参加→拡散→紹介などの循環を生み出します。
コミュニティ発信型のトレンド
Z世代のトレンドは、もはやマスメディアや大企業の一方的な仕掛けからは生まれにくくなっています。
代わりに、共通の価値観を持つ小さなコミュニティ=ミニマルコミュニティからの発信が火種となり、リアルな共感をベースに拡散していくのが特徴です。
その理由は、彼らが「つながるけど染まらない」などの価値観を持ち、自分らしさを認め合える小さな集団の中でこそ深い安心感や信頼を得られるからです。
具体的には、以下のような形でコミュニティからトレンドが生まれやすくなっています。
- リアルな共有
- 参加型コンテンツ
- 口コミとナノインフルエンサー
コミュニティ内での共感が発信の原点となるからこそ、トレンドは自然に広がり、最終的には「誰かに紹介したい」などのアクションに結びつきます。
企業にとっては、単に情報を届けるのではなく、ユーザーが共に作り上げたくなる環境を設計する必要があります。
まとめ|Z世代の流行を理解すればマーケティングで活用できる
Z世代の流行は、企業の一方的な仕掛けによって広がるものではなく、共感を起点とした自然な拡散によって形づくられます。
彼らが大切にしているのは「つながるけど染まらない」などの価値観であり、他者との共感を求めながらも自分らしさを失わないバランスを保つことです。
その結果、流行はナノインフルエンサーやUGCといった身近で信頼できる情報源から火がつき、ミニマルコミュニティのなかで共有され、やがて「会話の通貨」として拡散していきます。
だからこそ、企業がZ世代に向けたマーケティングを展開する際には、仕掛けの要素を前面に出すのではなく、共感や自己表現を支える体験を設計する必要があります。
Z世代が自然に「紹介したくなる」ような体験を提供できれば、流行は彼らの手によって広がり、結果として強いブランドロイヤルティを生み出すでしょう。