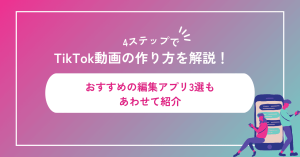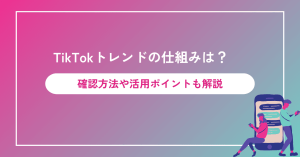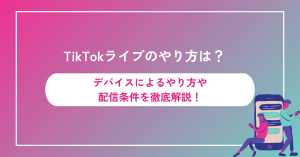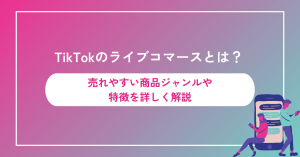TikTokのDM(ダイレクトメッセージ)機能の使い方やメリットを解説
TikTokのDM(ダイレクトメッセージ)機能は、ユーザー間で直接メッセージをやり取りできるコミュニケーションツールです。DM機能を活用することで、顧客やフォロワーとの距離を縮め、信頼関係の構築や効率的な問い合わせ対応が可能となります。
ダイレクトメッセージの送信設定や基本的な使い方を押さえれば、SNS運用の幅が広がり、マーケティング効果を高めることができます。ただし、使い方やプライバシー設定の注意点も把握しておくことが重要です。
そこで今回は、TikTokのDM機能の使い方やメリットを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
TikTokのDM機能とは?他のSNSとの違いや利用条件も解説

DM(ダイレクトメッセージ)とは
TikTokのDM(ダイレクトメッセージ)は、ユーザー同士が1対1またはグループで直接メッセージのやり取りができる機能です。テキストだけでなく、動画や画像、スタンプなど多彩なコンテンツが送受信でき、プライベートなコミュニケーションを実現します。
投稿へのコメントとは違い、内容が他者に見られることはありません。
他のSNSのDM機能との違い
InstagramやLINEのDM機能に似ていますが、TikTokは動画がメインプラットフォームのため、動画を直接DMで共有できる点が特徴的です。
また、DMの受信範囲はフォロー関係によって制限でき、「誰でも」「友達のみ」「オフ」など、プライバシー管理が細かく設定可能です。
既読機能もあり、相手がメッセージを読んだかどうかも確認できます。
DMの利用条件と対応端末
TikTokのDMは16歳以上のユーザーが利用可能です。DM機能はiOS・AndroidのTikTokアプリで使用でき、PCブラウザ版では対応していないことが多いです。
また、適切なプライバシー設定や相互フォローの関係が必要な場合があり、設定次第で利用範囲が変わります。送信できない場合は、アプリのアップデートやアカウント状態を確認してみましょう。
TikTokのDM機能の使い方

DM送信の基本的な操作手順
まずはTikTokアプリを開いて、DMを送りたい相手のプロフィールページにアクセスします。
プロフィール画面にある「メッセージ」アイコン(紙飛行機の形)をタップし、チャット画面でメッセージを入力、右下の送信ボタンを押して送信します。
複数の人を選択することでグループDMも作成可能です。
また、ホーム画面下部の「メッセージ」タブから既存の会話を選び、新規メッセージを送ることもできます。
メッセージの受信設定を変更する方法
TikTok設定から「プライバシー」→「メッセージ」の順に進み、「誰からメッセージを受け取るか」の設定を変更できます。
選択肢には「全員」「フォロー中の人」「誰からも受け取らない」があり、迷惑DM対策に利用可能です。
また、フォロー外のユーザーからのメッセージは「メッセージリクエスト」フォルダに入り、本承認後に通常のDM画面に表示されます。
画像や動画、リンクの送信方法
DMチャット画面の入力欄左の「+」アイコンやカメラアイコンをタップすると、画像や動画を送信できます。撮影したりスマホ内のメディアを選択して送信することも可能です。
また、メッセージ内に直接URLリンクを貼り付けることもできます。動画や画像は視覚的なコミュニケーション強化に役立ち、リンクは外部情報の共有に便利です。
TikTokのDM機能を活用するメリット

顧客との直接的なコミュニケーションを強化できる
TikTokのDM機能を使うことで、顧客と1対1で直接やり取りができ、細かなニーズや質問に迅速対応が可能です。これにより顧客満足度が向上し、信頼関係を築きやすくなります。
ビジネスアカウントでは自動メッセージ送信機能も活用でき、受付対応の効率化も図れます。
フォロワーエンゲージメントを向上させることができる
DMでのやり取りを通じてフォロワーとの交流を深めることは、エンゲージメント向上に直結します。
質問やコメントへの個別回答、キャンペーン案内などパーソナルな接触が増えることで、ファンのロイヤリティが高まるでしょう。
エンゲージメント強化はアカウントの成長や認知度UPにも寄与する重要なポイントです。
問い合わせ対応や販売促進への活用事例
DMを使った問い合わせ対応では、迅速な商品説明やサポートが可能となり、購入までの導線を強化できます。また、限定セールやキャンペーン情報をDMで直接配信し、販売促進に活用する事例も見られます。
個別メッセージでは視覚的な訴求もできるため、効果的な販促ツールとしても有効です。
TikTokでDM機能を利用する際の注意点とトラブル対策

プライバシー設定とメッセージ受信制限
TikTokでは「設定とプライバシー」メニューから「プライバシー」→「メッセージ」へ進み、DMを受信できる相手の範囲を「全員」「フォロー中のユーザー」「オフ」から選べます。これにより、知らない人からの迷惑メッセージを防げます。
設定変更は簡単ですので、必要に応じて調整しながらプライバシー保護を徹底しましょう。
不適切なメッセージへの対応方法
不快なDMが届いた場合は、メッセージ内のメニューボタンから「ユーザーをブロック」や「報告」が可能です。これにより該当ユーザーからのメッセージ受信を停止し、TikTokへも通報されます。
定期的にDMの内容をチェックし、自分や企業の安全を守ることが重要です。
送信できない・届かない原因と対処法
DMが送れない理由としては、相手のプライバシー設定が制限されている場合や、自分が相手にブロックされているケースがあります。また、アプリの不具合や通信環境の不安定さも原因となります。
このような場合は、アプリの最新版に更新し、通信環境を見直すのがおすすめです。また、相手と連絡を取り合って設定を確認するのも有効です。
企業のSNS運用におけるDM戦略のポイント

DMを使ったリード獲得とフォローアップ
TikTokのDM機能は、見込み顧客との直接コミュニケーションに活用でき、リード獲得後の個別フォローアップが効果的です。
例えば、動画内やプロフィールに問い合わせや資料請求への誘導を設置し、DMで詳細情報やサポートを提供して関心度を高めることが可能です。
獲得したリードには迅速かつパーソナライズされた対応を行うことで、商談や購入につなげやすくなります。
イベントやキャンペーンでのDM活用法
限定イベントやキャンペーン情報をDMで直接送信し、参加促進や特典案内に活用します。
例えば、応募者への当選連絡やイベント案内、クーポン配布などを個別に行うことで、参加率を高め、顧客ロイヤルティの向上が期待できます。
このように、双方向のコミュニケーションが可能なDMは、会話型マーケティングの強力なツールなのです。
オートメーションツールとの連携の可能性
DMの自動応答やフォローアップ機能を持つオートメーションツールと連携することで、24時間の顧客対応が実現可能です。リード情報の管理や段階的なナーチャリングに便利で、効率的な運用が可能となります。
TikTok向けのCRM連携やチャットボット活用も進んでおり、人的コスト削減と同時に顧客体験の向上に寄与します。
企業がDMを効果的に運用するコツ

メッセージ内容の工夫とテンプレートの活用
DMの文面はパーソナルで親しみやすく、相手のプロフィールや行動を踏まえた内容にすることがポイントです。
例えば、感謝や共感を伝えるテンプレートを用い、相手だけの特別感を演出します。明るくポジティブな表現や季節・トレンドを織り交ぜることも効果的です。
ビジネスでは依頼や案内文の例文を用意し、効率的ながらも丁寧なコミュニケーションを図りましょう。
送信タイミングと頻度の最適化
DM送信は相手のアクティブ時間を意識し、週に1〜2回程度の頻度が望ましいです。過剰な送信はスパム認定やフォロワー離れの原因になるため避けましょう。
イベントやキャンペーンの前後、ユーザーの反応タイミングで送ることで開封率や反応率が高まります。定期的に分析を行い、最適なタイミングを見極めることが成功に繋がるポイントです。
フォロワーとの信頼関係構築に向けたコミュニケーション術
返信は迅速かつ丁寧に行い、相手の疑問や要望に真摯に対応する姿勢が重要です。
単なる宣伝ではなく、対話ができる「人間味のあるコミュニケーション」を目指しましょう。加えて、相手のフィードバックを活かし、コンテンツ改善やサービス向上に反映させることで信頼感が高まります。
このような取り組みが、フォロワーのロイヤルティ強化と継続的なエンゲージメントにつながる要因です。
ZIKのSNS運用コンサルティングを活用するメリット

DM機能を活かしたSNS戦略立案支援
ZIKのコンサルティングは、TikTokをはじめとしたSNSでのDM機能を含む双方向コミュニケーションを戦略的に活用する支援を行います。
ターゲット層の行動分析や競合調査を踏まえ、効果的なDM活用によるリード獲得や顧客フォローアップの設計が可能です。
これにより、企業のSNS戦略がより高度化かつ実践的になります。
運用代行やトラブル対応の専門サービス
ZIKは日々の投稿運用はもちろん、DM対応やコメント管理、炎上リスクの監視・対応まで包括的にサポートします。
専門知識と豊富な経験を持つスタッフが担当するため、トラブルの際にも迅速かつ適切な対応でブランドイメージを守ることが可能です。
これにより、社内リソースの負担軽減はもちろん、SNS運用の質の向上を実現します。